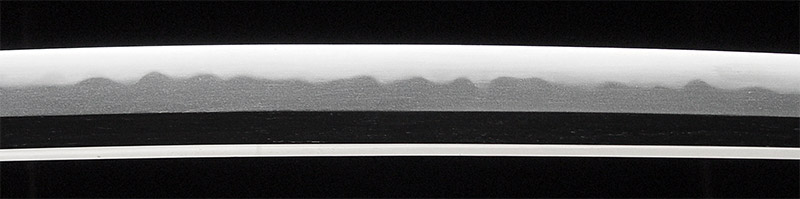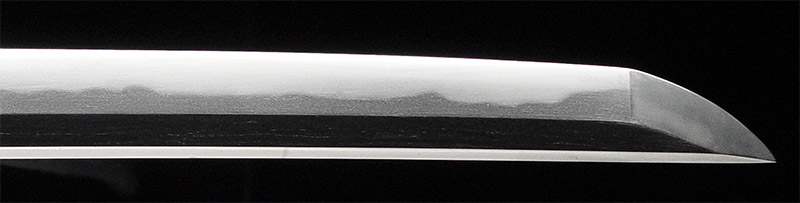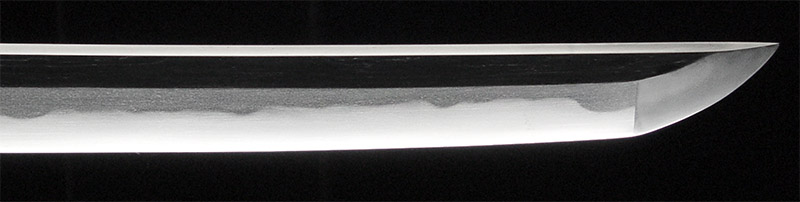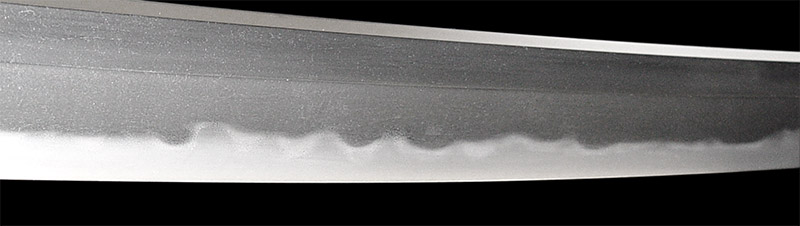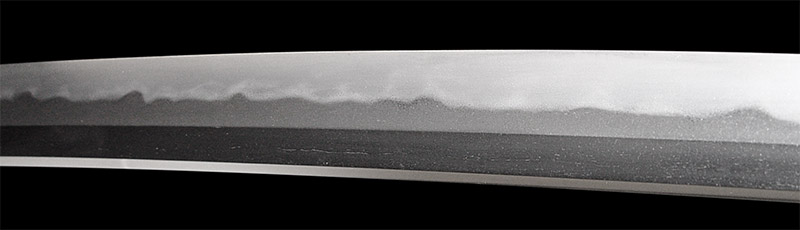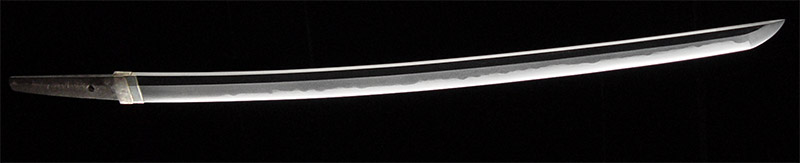日本刀 ¤ 刀 ¤ 武州住吉正作之 寛文元年八月日 ¤業物
表/武州住吉正作之 裏/寛文元年八月日
Katana /
Omote / Bushu ju Yoshimasa kore wo tsukuru
Ura / Kanbun 1 nen 8 gatujitsu
- 長さlength
- 62.3cm
- 反りsori
- 1.3cm
- 目釘穴mekugi
- 1個
- 元幅
- 3.25cm
- 先幅
- 2.35cm
- 元重
- 0.8cm
- 時代
- 江戸初期 寛文元年(1661年)
- period
- early edo (1661)
- 国
- 武蔵-土佐(東京-高知)
- country
- musashi-tosa
- 刃文
- 互の目丁子
- hamon
- gunome choji
- 地鉄
- 小板目
- jigane
- ko-itame
- 帽子
- 小丸
- boshi
- komaru
- はばき
- 銀着二重
- habaki
- silver foil double
- 外装
- 肥後拵・白鞘
- mounting
- koshirae & shirasaya
- 鑑定
- 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書附
- Certificate
- [N.B.T.H.K] tokubetsu hozon token
- 正価
- 売却済
- price
- Sold
吉正は美濃関の出身で江戸にて活躍し、その後土佐へ移住。虎徹や安定と関係があると云われ、強い地鉄で作柄も似ている。切り銘は他に上野介吉正や武州住田中源左衛門尉吉正などがある。
本作は身幅重ね厚い豪壮な姿。互の目丁子刃文は焼出しで始まり、切先に掛けて徐々に焼き幅を高くする。刃縁は沸がたっぷりと付き、小足無数に入って尖り刃も交え華やか。小板目肌には地沸と地景が全体に見られ、帽子は焼き深く小丸に返っている。生ぶ茎は錆色良く、珍しく年期も切られ貴重。
付属する拵は典型的な肥後拵で、金具も肥後物で揃える。茶石目地鞘に茶裏皮巻の柄前。鉄地に唐草を象嵌した縁頭に、金地菊花目貫。鐔は肥後神吉の鉄地干海鼠図で保存刀装具鑑定書付。神吉派は肥後藩の命により林派に習い、後に細川家のお抱えとして活躍した名工。派手さはないが玄人受けする雅味ある拵は大変飾り映えする。特別保存刀剣鑑定書附。